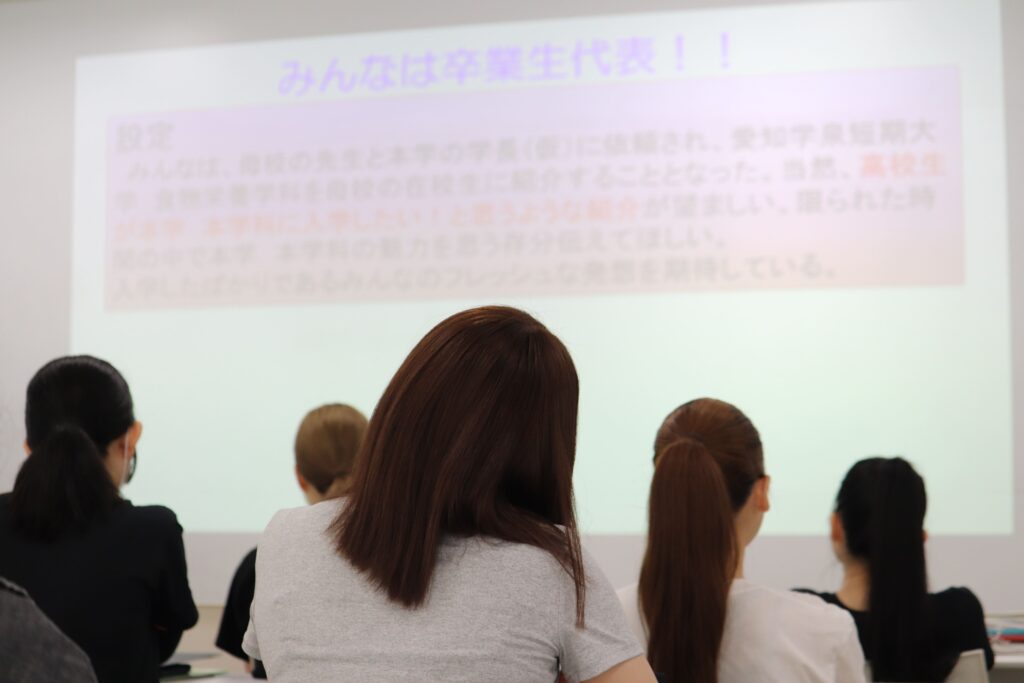学泉の学びレポート 短大編 #10|1人で45食,50人で1食?――“格差”を体感する経済の授業
📚✨\経済を“わたしのこと”として考える――価値観が揺れる授業/✨📚
こんにちは!学生募集室の運営23号です🕊️
今日も,愛知学泉大学・愛知学泉短期大学の学びの現場から,心に残る講義の様子をお届けします!
今回取材したのは,愛知学泉短期大学 生活デザイン総合学科の《経済のしくみ》第3回講義です📖
一見むずかしそうに見える「経済学」ですが,この授業では“わたしの暮らし”とつながる視点からアプローチする工夫がたっぷり詰まっていました!
💬前回のふりかえりからスタート
講義は,まず前回の内容のふりかえりからスタート📘
「貝殻が貨幣として使われている国があること」や,「“公”と“私”の価値観のちがい」など,
“経済”と聞いてイメージするものとは一味ちがう切り口に触れた学生たちのコメントが次々と披露されます。
✍️振り返りシートで深まる「自分ごと」
この授業のユニークなところは,学生が書いた振り返りシートの紹介に,たっぷり時間を使っていること!
先生は,「経済学を知識としてではなく,自分の価値観や経験と重ねて考えてほしい」という思いから,
ひとつひとつのコメントを丁寧に取り上げていきます✨
この日紹介された振り返りコメントの一部をご紹介します:
・「経済は,思っていたより人の価値観に左右されている」
・「なぜ人は,お金に価値を見出したのか」
・「どうすれば,お金の価値を変えることができるのか」
・「世界の富の8割を裕福な人が独占しており,2割の私たちが分け合っているという言説を見たことがある」
・「目的があってアルバイトをしているのに,アルバイトに翻弄されてその目的を達成できていないのは本末転倒」
・「キャッシュレスが増えている日本において,社会的価値として紹介された貝殻貨幣をどうこう言うことは難しい」
・「日本も昔は物々交換していた?」
どれも,まさに“自分ごと”。
つまり,学生自身の関心領域から経済に向き合おうという視点が伝わってきます🧠✨
🍽️もしも「世界の富」が給食だったら…
とりわけ,「世界の富の8割を裕福な人が独占している」というコメントには,
先生も熱を込めて解説。
実際に,「世界の富の約45%を上位1%の富裕層が保有し,下位50%の人々で,わずか1%の富を分け合っている」
という調査結果があることを紹介しました。
……こう聞くと,「すごい格差だな」と思うけれど,
数字を聞いても今ひとつピン来ません。
そこで,先生はすかさず
「じゃあ,もしこれが給食の配膳だったらどうなるでしょう?」
たとえば,100人の教室があったとして,給食は全部で100食。
でも,そのうち1人だけが45食分をもらって,
次に裕福な9人が35食分を山分け,
その次の40人が19食分を分け合って,
最後の50人は,たった1食分をみんなで分けている――そんな状態です。
1人だけが45食も並べ食べられるわけがない。そのほとんどはロス,捨てられる。
しかし,同じ教室の半分の生徒は,ほんのひとくちずつしか食べられない。
そう思うと,この“分け方”がいかに偏っているかが,
数字以上にリアルに感じられてきます。
🧀お金とつながりのあいだで
「日本も昔は物々交換していたのでは?」というコメントからは,
経済と人との関係性についても話が広がりました。
先生は,「お金は便利だけど,人との関係を切ってしまう一面もある」と語り,
ご自身の体験として,
「1日引っ越し作業を手伝ってくれた仲間たちへのお礼に,タイヤサイズのチーズを取り寄せて手料理を振る舞った」
というエピソードも披露🧀✨
引っ越しをサービスとしてアウトソーシングするのでなく,ある種のイベントにして
労働と感謝という”価値の交換”が持つあたたかさや信頼の感覚が,学生たちの心にも残ったようでした。
💡「市場」ってなんだろう?
講義の後半では,「市場の成り立ちと,価格の決まり方」がテーマに📈
先生は,「“経済”という言葉が市場の説明にそぐわない」とする視点から,
ギリシア語を語源とする「カタラクシー:交換」という言葉を紹介。
モノやサービスのやり取りが,感情や関係性のなかでどう成立していくかに着目した温故知新の視点が提示されました。
📘次回はどんなふりかえりが飛び出すか!?
毎回,学生たちの素直な言葉が,授業の内容をさらに深めてくれる「経済のしくみ」。
次回は,今回の講義を受けて,どんな視点が寄せられるのか…楽しみです🕊️✨
🕊️学科の詳しい情報はこちらから👇
🔗生活デザイン総合学科
📝ほかの【学泉の学びレポート短大編】もあわせてチェック!
🔗記事一覧はこちら